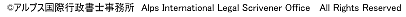はじめに~相続手続きの開始
相続人と相続財産の確定
遺言書の効力と重要性
遺産分割協議と協議書作成
遺産の評価と相続税
ご相談メール(SSLにて暗号化)
お電話・FAXにてお問い合わせ
TEL/FAX 0166-75-5750
事務所のご紹介と経営理念
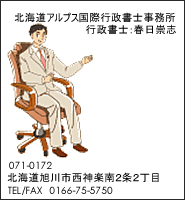

預貯金の払い戻し
相続人が一人しかいない場合、あるいは親子だけの場合などを除いて、故人の預貯金の口座については、閉鎖しておいた方が良い場合があります。これは、親族などによって預貯金が勝手に引き出されることを防ぐためです。銀行などの金融機関は、預金者が死亡した時点で、その口座を閉鎖することになっています。しかし、金融機関側が毎日預金者の存否を確認しているわけではないので、実際には、遺族などが口座の閉鎖を申し出ます。
しかしながら、故人の預貯金を払い戻す必要があるときも少なくありません。故人の預貯金が払い戻すことができなければ、残された遺族の当面の生活費や故人の入院費用、葬儀費用の支払いに困るときがあります。そのようなときは、故人の戸籍謄本に、法定相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書などを添えて銀行の所定の用紙に記入し提出します。
故人が金融機関の貸金庫を利用している場合も同様です。貸金庫の場合には、もともと何が入っていたか故人しか知らない場合が多く、金融機関の通帳のように戻したものが記帳されるわけではありませんので、あとから「入っていた」「入っていなかった」等のトラブルを防ぐためにも、相続人全員か、第三者とともに開けるとよいでしょう。
生命保険金の請求
故人が生命保険に加入していたときには、まず生命保険証券を探し、保険会社に連絡します。そして、その保険証券の死亡保険金の受取人が誰になっているかを確認します。受取人として特定の方の氏名が記載されている場合には、その受取人が請求します。受取人が指定されていない場合や法定相続人が指定されている場合には、法律で定められた相続人全員(後述します)が受取人となります。死亡診断書、故人の戸籍謄本、受取人の戸籍謄本、受取人の印鑑証明書などを添付して保険会社に請求します。実はこの受取人が誰になっているか、誰が保険料を支払っていたかのかで、誰が相続税を支払うか変わってきます。いずれも多少複雑ですので、当事務所へご相談ください。
遺族年金の受給の手続き
公的年金には主に国民年金と厚生年金があります。誤解が多いところですが、厚生年金加入者は国民年金にも加入しています。つまり、国民年金だけに加入している方は1階建ての年金ですが、厚生年金に加入している方は2階建ての年金となります。国民年金だけに加入している夫が故人となったときには、妻と子供に「遺族基礎年金」が支給されます。また、婚姻期間が10年以上あった夫婦で、妻が60歳から65歳になるまでの最長5年間は「寡婦年金」を受け取ることができます。支給金額は、死亡した夫が受け取る予定だった老齢基礎年金の年金額の4分の3に相当する額です。さらに、前述の「遺族基礎年金」も「寡婦年金」も支給されない場合においては、「死亡一時金」が支給されます。死亡当時、生計を同じくしていた配偶者・子・孫・祖父母または兄弟姉妹の順で請求できます。ただし、「寡婦年金」と「死亡一時金」は併せて受給することができないので、どちらかを選択することが必要です。死亡一時金の支給額は、故人が保険料を納めた期間によって12万円から32万円の間です。
故人が厚生年金に加入していた場合には、「遺族厚生年金」が支給されます。死亡した保険加入者によって生計を立てていた配偶者・子・父母・孫・祖父母の順で請求できます。また、遺族厚生年金の加算で、遺族厚生年金を受給する遺族の妻が遺族基礎年金を受けられないときに、35歳以上の妻(35歳未満でも、子供が18歳になったとき妻の年齢が35歳以上の場合も含む)は、40歳から65歳になるまで「中高齢寡婦加算」を受給することができます。支給額は、年額でおよそ60万円弱です。
また、故人が65歳以上になっていたなど、すでに老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給していた場合には、その年金の給付を中止する手続が必要となります。
葬祭費、埋葬料の請求
あまり知られていないことですが、故人が国民健康保険や勤務先の健康保険組合に加入していた場合には、葬祭費または埋葬料を請求できます。請求には、健康保険証のほか、死亡診断書や葬儀費用の領収書などを提出します。
以上が主な請求の手続ですが、請求の種別により必要な書類を見極めたり集める必要があることのほか、それぞれ一定の期間請求をしないと請求する権利が時効により消滅してしまいますので、請求漏れを防ぐためにも、アルプス国際行政書士事務所へご相談ください。
行政書士には、法律上みなさまの秘密を漏らしてはならない義務が課せられておりますので、安心してお問い合わせください。
TEL/FAX:0166-75-5750 メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
- ~万一に備えて~遺言書作成
- 自筆証書遺言| 秘密証書遺言| 公正証書遺言| 遺言信託| 遺言書の内容の変更| 遺言書の開封| 成年後見制度|
- ~遺志を受け継ぐ~遺産分割協議
-
亡くなったときの手続き|
死亡届の提出|
葬儀の手配と喪主・世話人の決定|
契約の解約・名義変更|
資格・免許の返納|
預貯金の払い戻し・貸金庫の開庫|
生命保険金の請求|
遺族年金・死亡一時金の受給手続き|
葬祭費・埋葬費の請求|
法定相続人とは| 法定相続分とは| 限定承認とは| 相続放棄とは| 相続欠格・相続排除とは| 特別受益・寄与分とは|
遺言書の効力と検認手続き| 自筆証書遺言| 公正証書遺言| 秘密証書遺言| 遺言信託| 遺産分割協議と協議書作成| 遺産分割調停| 遺産分割審判| 不動産の所有権移転登記| 課税財産と非課税財産| 宅地の評価| 建物の評価|
賃借権の評価| 株式・公社債の評価| その他の遺産の評価| 相続税の計算と節税対策| 相続の法律に関するご相談|